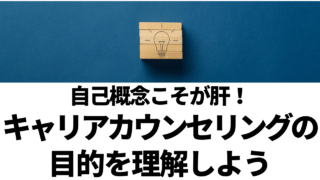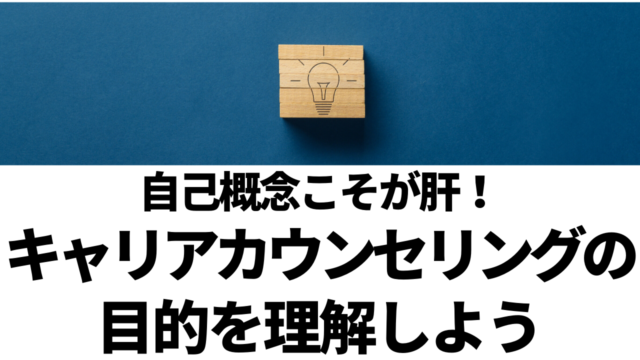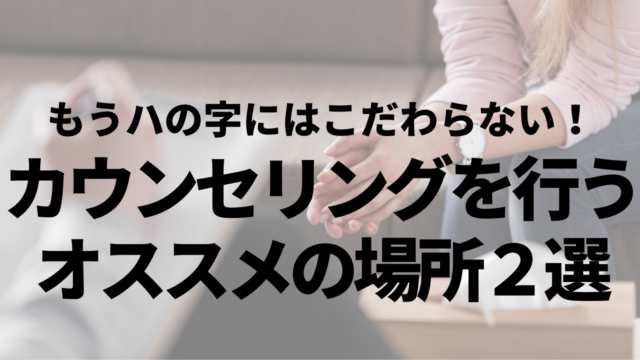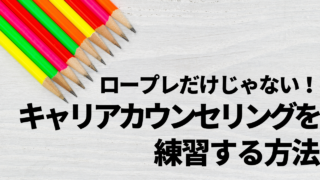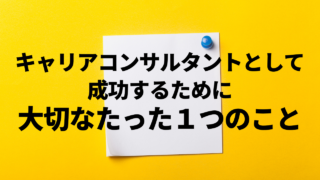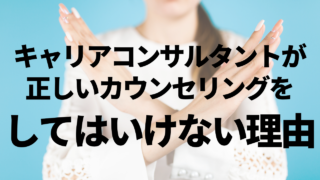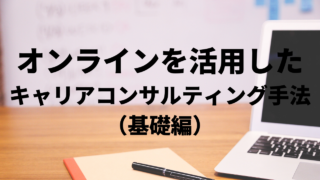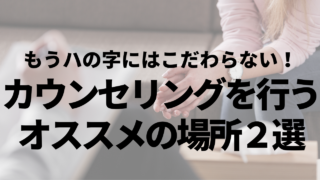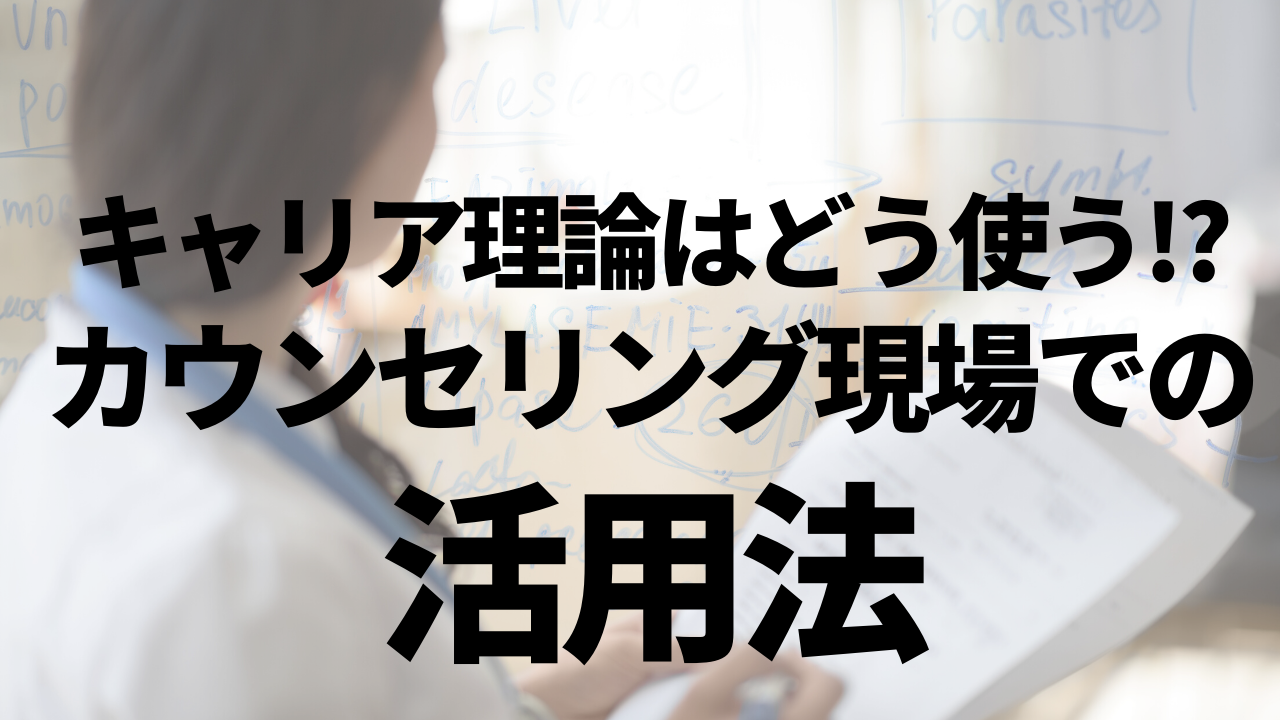
こんにちは、岩橋ひかりです。
この記事では、実際のキャリアカウンセリングの現場で、キャリア理論をどのように使えばいいのかということについてお伝えします。
これまでに学んできたキャリア理論を実際のカウンセリングへの活かす方法がわかるようになりますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。
キャリア理論の使い方
キャリアコンサルタントの方々は、多くのキャリア理論についてたくさんの時間をかけて勉強してきたと思います。
そしてまた、資格取得後も様々なキャリア理論の学びを深めている方もいらっしゃると思います。
ですので、キャリアカウンセリングをするうえでも、
・キャリア理論に基づいてクライエントを導けるか
ということを気にしてしまう方も少なくないかもしれません。
もちろん、こうしたキャリア理論が大切なのは事実です。
しかし、「キャリアコンサルタントが正しいカウンセリングをしてはいけない理由」でお伝えしたように、キャリアカウンセリングの1番の目的は、「クライアントが変わること」、つまりクライアントの行動が変わっていくことです。
このことはカウンセリングをする間、常に念頭に置いておいていただきたいことです。
なので、まず意識すべきは
クライアントが求めていることや望み、どんなことを考えているか
について、じっくりと聞いていくことがスタート。
いろいろと話を聞いていく中で、「この場合はこの理論の話が役に立つのでは」、「この場合はこの理論が当てはまりそう」、と感じられるようになってくるので、そこで初めて理論の話をクライエントにしていくのが良いと思います。
女性のキャリア支援で使う理論
私がよく使う理論として、例えば、キャリアの偶然の力、「プランド・ハプンスタンスセオリー」があります。
私のクライエントは働く女性の方々なので、
- 思いがけない異動の打診があった
- 旦那さんが転勤になってしまって自分のキャリアが描けなくなってしまった
- 出産後体調を崩し、以前のようにバリバリ働けなくなってしまった
ショックなことが起きてガーンとなってしまっている人に対して、「偶然の力がキャリアを変えることがあるんですよ」ということを提示することができると、「そういう考え方もあるんだ」と、ちょっとホッとされるという場面をこれまでに何度も経験してきました。
また、転機をどのように生かしていくかというシュロスバーグの「転機の理論」もよく使います。
思いがけないことが起きる、あるいは逆に思っていたことが起きない、例えば子供を望んでいるのだけれどなかなか子宝に恵まれない、夫の転勤に備えているのにいつまでも転勤しない、といったことで悩んでいる時に、では実際どうなのかということを理論に当てはめて説明したりしていました。
また、これはキャリア理論ではありませんが、マズローの「欲求の5段階説」があります。例えば、仕事と家庭の両立に苦しみ、この先のキャリアが描けないと悩んでいるワーキングマザーの方によくよくお話を聞いてみると、ゆっくり食事をする時間がなかったり、寝不足だったり、お手洗いも満足に行けないなど生理的な欲求が満たされていない状況でした。そんな状態で自分のキャリアについて考えようとしても、難しいのは当然です。
クライエントによって使い分ける
このように、目の前にいるクライアントが話している内容を聞き、うまく当てはまりそうな理論があれば提示する、という使い方をしています。
また、クライアントの状況がぴったり当てはまる理論があったとしても、必ずしもそのクライエントが理論の知ることが必要かというと、そうでもない場合もあります。
感情的だったり、固い話をするより自分の話を聞いてほしい方、気持ちに即した話をした方が納得していただきやすい方であれば、理論の話をしてしまうことで、「なんかこの人私の話を全然聞いてくれない」ということにもなりかねません。
全てはクライアントが変わること、クライアントが求めていることを提供することがスタート。理論は必要な時に提示すれば良いのです。キャリアコンサルタントだからキャリア理論を使わなければいけないということはないですし、私のこれまでの経験では、キャリア理論を求めてキャリアコンサルタントに相談に来たという方は一人もいません。
まとめ
この記事のまとめです。
キャリア理論は、クライエントが必要としている時、理論を使って説明したほうが理解してもらいやすそうなときだけに使う

このセミナー動画では「キャリアコンサルタントに特化した集客の基礎3ステップ」を90分でお伝えします。WEB初心者でもわかりやすく実践的な内容です。
- キャリアコンサルタントだからこそできる集客手法
- 一般のキャリアコンサルタントが集客できない理由
- WEBを活用したクライエント獲得法 などをお伝えしています。
キャリアコンサルタントとしての活躍に向けて、ぜひご活用ください。